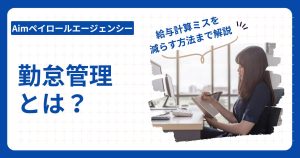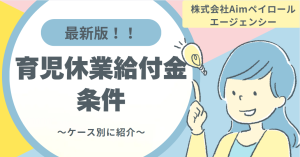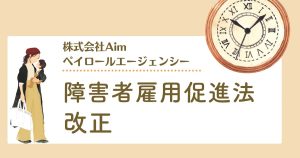「顧客からの過剰な要求や理不尽なクレーム、いわゆる『カスタマーハラスメント(カスハラ)』にどう対応すればいいのか」「法改正で対策が義務化されると聞いたが、何から手をつければいいか分からない」。
これまで個別の対応に留まりがちだったカスハラ問題ですが、社会的な問題の深刻化を受け、ついに法的な枠組みが整備されることになりました。
2025年に公布された改正労働施策総合推進法により、2026年中の施行が予定されており、すべての企業に対して従業員をカスハラから守るための対策を講じることが義務付けられます 。
本記事では法改正の重要なポイントから、企業が具体的に取り組むべき対策、そして対策を怠った場合のリスクまで、分かりやすく解説します。
- カスハラ対策の法改正のポイント
- カスハラ対策義務化のスケジュール
- カスハラに該当する具体例
【2025年】カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化とは?
まず、「義務化」の根幹となる法律の概要と、そもそも何が「カスハラ」にあたるのか、その定義から正確に理解することが不可欠です。このセクションでは、法改正の全体像を把握するための基礎知識を解説します。
厚生労働省による「カスタマーハラスメント」の定義
厚生労働省は、2022年に公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の中で、カスハラを以下のように定義しています 。
「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」
この定義を理解する上で重要なポイントは、大きく2つあります。
- 要求内容の妥当性:顧客の要求に、企業の提供する商品やサービスに関する正当な理由があるか。
- 手段・態様の相当性:要求を伝える方法が、社会の常識に照らして許容される範囲内か。
つまり、すべてのクレームがカスハラに該当するわけではありません。
商品やサービスに不備があった場合の正当な要求は、企業が真摯に対応すべきものです。しかし、要求内容に妥当性があったとしても、その伝え方が暴力的であったり、脅迫的であったり、あるいは何度も執拗に繰り返されたりする場合は、カスハラに該当する可能性があります 。
そして、この定義の最後にある「労働者の就業環境が害されるもの」という部分が、企業責任と直結する極めて重要な要素です 。従業員が精神的・身体的な苦痛を感じ、安全に働けない状況に陥ることを、企業は放置してはならないのです。
2025年に公布された改正労働施策総合推進法がポイント
今回のカスハラ対策義務化の法的根拠となるのが、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、通称「労働施策総合推進法」の改正です 。
この法律は、これまでも職場におけるパワーハラスメント防止措置を事業主の義務として定めてきました 。今回の改正は、その対象を顧客等からの著しい迷惑行為、すなわちカスハラにまで拡大するものです。これは、国が職場におけるハラスメント対策を包括的に強化し、労働者保護の姿勢をより鮮明にしたことを意味します。
また、法律が対象とする「顧客等」の範囲は非常に広い点にも注意が必要です。単なる商品購入者やサービス利用者だけでなく、取引先の担当者、病院や公共施設の利用者、さらには将来顧客になる可能性のある人や、近隣住民といった事実上の利害関係者も含まれると解釈されています 。
なぜ今、義務化されるのか?(背景)
カスハラ対策が法的な義務として位置づけられた背景には、いくつかの深刻な社会的要因があります。
第一に、カスハラ被害の深刻化です。従業員に対する暴言や脅迫、長時間の拘束、土下座の強要といった悪質な行為は、被害を受けた従業員に深刻な精神的ダメージを与え、うつ病などの精神疾患や休職、離職につながるケースが後を絶ちません 。これは個人の問題に留まらず、企業の貴重な人材の損失であり、生産性の低下にも直結します。
第二に、日本の社会に根強く残る「お客様は神様」という価値観の歪んだ解釈です。この考え方が、一部の顧客による理不尽な要求を助長する土壌となってきました 。従業員個人が耐えるだけでは限界があり、企業、そして社会全体で労働者を守るための明確なルールが必要とされたのです。
この法改正は、行き過ぎた顧客至上主義に一線を画し、「顧客への誠実な対応」と「従業員の尊厳と安全の確保」を両立させなければならないという、新しい時代のサービス業の在り方を示すものと言えます。
企業がカスハラに対して毅然とした態度を示すことは、従業員を守るだけでなく、大多数の良識ある顧客にとっても、より質の高いサービスを受けられる健全な環境づくりに繋がります。
対象となる企業(全事業者が対象)
今回の法改正で最も重要な点の一つは、カスハラ対策の義務が、企業の規模や業種を問わず、すべての事業主に課されるということです。従業員を一人でも雇用していれば、大企業はもちろん、中小企業や個人事業主も対象となります。
「うちは小さな会社だから関係ない」「専門の担当者を置く余裕がない」といった理由で対策を先送りにすることはできません。むしろ、限られた人員で事業を運営する中小企業こそ、一人の従業員がカスハラによって心身の不調をきたした場合の経営へのインパクトは計り知れません。自社の実情に合った、実行可能な対策から着実に進めていくことが求められます。
【いつから?】2025年のカスハラ対策義務化のスケジュール
法改正の概要を理解した次に担当者が知りたいのは、「具体的にいつから対応が必要になるのか」というスケジュール感でしょう。ここでは、施行時期と今後の動向について解説します。
施行は2025年6月から1年6月を超えない範囲内で定める日
カスハラ対策を盛り込んだ改正労働施策総合推進法は、2025年6月11日に公布されました 。法律の条文によると、カスハラ対策に関する規定の施行日は「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされています 。
これは、法律の公布から最大18ヶ月以内に施行されることを意味しており、遅くとも2026年12月までには義務化が開始されることになります。多くの専門家は、準備期間を考慮し、2026年度中の施行を予測しています 。
今後発表される「指針」に注目
法律そのものは、企業が対策を講じるべき義務があるという「骨格」を定めたものです。では、「具体的に何をどこまでやれば義務を果たしたことになるのか」という詳細な内容は、今後、厚生労働省が公表する「指針(ガイドライン)」によって示されることになります 。
これは、先行して義務化されたパワーハラスメント対策と同様の手法です。パワハラの際も、法律の施行と合わせて詳細な指針が示され、多くの企業がその指針を基に具体的な社内ルールや研修内容を策定しました 。
したがって、企業の担当者は、厚生労働省のウェブサイトなどを定期的に確認し、この「指針」がいつ発表されるのか、どのような内容が盛り込まれるのかを注視し続ける必要があります。指針が公表され次第、速やかに自社の対策に反映させることが、スムーズな法対応の鍵となります。
2025年のカスハラ対策の改正法で定められた企業の義務【具体的に何をすべきか】
ここからは、「企業が具体的に何をすべきか」について、パワハラ防止指針で示された4つの柱を参考に、詳しく解説していきます。これらは、今後発表されるカスハラ対策の指針でも同様の枠組みが求められると予想されます。
① 事業主の方針等の明確化と周知・啓発
対策の第一歩は、経営トップが「我が社はカスタマーハラスメントを容認せず、従業員を断固として守る」という明確な方針を内外に示すことです 。このトップの強い意志が、すべての対策の土台となります。
具体的なアクションとしては、以下のものが挙げられます。
就業規則への明記
就業規則に、カスハラの定義や禁止行為、発生時の対応方針、相談窓口などを具体的に記載します。これは、社内における公式なルールとして対策を位置づける上で不可欠です。
社内での周知・啓発
ポスターの掲示や社内報、イントラネットなどを活用し、会社の方針を全従業員に繰り返し伝えます。単にルールを伝えるだけでなく、「一人で抱え込まずに相談してください」というメッセージを添えることが重要です 。
研修の実施
管理職向け、一般従業員向けなど、階層に応じた研修を定期的に実施します。カスハラとは何か、どのような言動が該当するのか、発生時にどう行動すべきかを具体的に学びます 。
② 相談に応じ、適切に対応するための体制整備
従業員が安心して声を上げられる「相談窓口」の設置は、法律で明確に求められる措置です 。この窓口が形骸化せず、実際に機能することが極めて重要です。体制整備のポイントは以下の通りです。
相談担当者の設置
人事部や総務部の担当者など、相談に対応する人員を明確に定めます。担当者には、守秘義務の重要性や傾聴のスキル、対応プロセスの知識など、専門的な研修を受けさせることが望ましいです。
相談方法の多様化
対面だけでなく、電話、メール、専用のウェブフォームなど、従業員が利用しやすい複数の相談チャネルを用意します。
プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止
相談者のプライバシーは厳守し、相談したことを理由に解雇や降格などの不利益な扱いをしてはならない旨を規定し、全従業員に徹底して周知します 。
参考【すぐに使える】相談窓口設置のチェックリスト
自社で相談窓口を設置・運用する際に、漏れがないかを確認するためのチェックリストです。
カスタマーハラスメント相談窓口 設置・運用チェックリスト
| No. | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 相談窓口の担当部署・担当者を正式に決定したか? |
| 2 | 担当者に対して、守秘義務や対応手順に関する研修を実施したか? |
| 3 | 対面、電話、メールなど、複数の相談方法を設けたか? |
| 4 | 相談受付時間や連絡先を明確に定めたか? |
| 5 | 外部専門家(弁護士、産業医等)との連携体制を構築したか? |
| 6 | 相談受付後の対応フロー(事実確認、報告ルート等)を文書化したか? |
| 7 | 相談者や関係者のプライバシー保護に関するルールを定めたか? |
| 8 | 相談等を理由とする不利益な取り扱いを禁止する旨を就業規則等に明記したか? |
| 9 | 相談窓口の存在と利用方法を全従業員に周知したか?(ポスター、イントラネット等) |
| 10 | 管理職に対し、部下から相談を受けた際の対応方法について研修を行ったか? |
③ 被害労働者への配慮のための取組
企業の責任は、ハラスメント行為を止めさせることだけで終わりません。被害を受けた従業員の心と身体のケアこそが、最も優先されるべき事項です 。
具体的には、以下のような配慮が求められます。
メンタルヘルスケア
被害を受けた従業員の精神的な負担は計り知れません。産業医や保健師、カウンセラーによる面談の機会を速やかに設ける、あるいは提携しているEAP(従業員支援プログラム)サービスを紹介するなど、専門的なケアに繋げる体制を整えます 。
就業上の措置
従業員の状況に応じて、一時的に顧客対応業務から外したり、配置転換を行ったりするなど、安心して回復に専念できる環境を整えます。必要であれば、特別休暇の付与も検討します。
継続的なフォロー
一度の面談で終わらせず、その後も定期的に上司や人事担当者が状況を確認し、孤立させないように寄り添う姿勢が重要です。
④ ①〜③の措置と併せて講ずべき措置
上記の3つの柱を効果的に機能させるためには、それらを統合し、一貫した対応プロセスを構築する必要があります。
迅速かつ正確な事実確認
相談があった場合、まずは相談者の安全を確保した上で、客観的な事実関係を迅速に確認します。相談者と行為者(顧客)、そして目撃者がいれば第三者からも話を聞きますが、その際は双方のプライバシーに最大限配慮します 。
行為者(顧客)への対応
事実確認の結果、カスハラ行為が認められた場合、あらかじめ定めた社内ルールに基づき、行為者に対して警告、サービスの提供拒否、悪質な場合は警察への通報など、毅然とした対応をとります 。
再発防止策の検討
発生した事案を個別の問題として終わらせず、なぜ起きたのか、どうすれば防げたのかを組織として分析します。その結果をマニュアルの改訂や研修内容の見直しに活かし、組織全体の対応能力を高めていくPDCAサイクルを回すことが重要です 。
2025年のカスハラに該当する具体例
法律の定義や企業の義務を理解しても、現場で「この言動はカスハラなのか、それとも厳しいだけの正当なクレームなのか」と判断に迷う場面は少なくありません。ここでは、具体的な言動の例を挙げながら、その境界線について解説します。
カスハラに該当する可能性のある言動(具体例)
厚生労働省のマニュアルなどでは、以下のような言動がカスハラの典型例として挙げられています 。
- 身体的・精神的な攻撃
- 暴行、傷害(物を投げつける、胸ぐらを掴むなど)
- 脅迫(「殺すぞ」「家に火をつけるぞ」などの発言)
- 名誉毀損、侮辱、ひどい暴言(人格を否定する言葉、差別的な発言)
- 威圧的な言動
- 大声で怒鳴りつける、机を叩くなどして相手を威嚇する
- 従業員を長時間にわたり詰問する
- 土下座での謝罪を強要する
- 継続的・執拗な言動(リピート型)
- すでに解決済みの問題について、何度も電話をかけたり来店したりしてクレームを繰り返す
- 業務に支障が出るほど長時間、電話を切らせない、店舗から退去しない(居座り)
- 不合理・過剰な要求
- 自社の製品・サービスとは無関係な要求(「誠意を見せろ」と金銭を要求するなど)
- 社会通念上、過剰な見返り(慰謝料など)を要求する
- 従業員個人の連絡先を教えるよう強要する
- プライバシー侵害・SNSでの誹謗中傷
- 従業員の許可なく写真や動画を撮影し、SNSなどに公開する
- 従業員の実名を挙げて、ネット上で誹謗中傷する
- セクシュアルハラスメント
- 不必要な身体的接触
- 性的な冗談や容姿に関する発言
正当なクレームとの違い
正当なクレームとカスハラの境界線は、前述した「要求内容の妥当性」と「手段・態様の相当性」という2つの軸で判断します 。現場での判断を助けるため、以下の表に具体的な違いをまとめました。この表は、社内研修の資料としても活用できます。
正当なクレームとカスタマーハラスメントの境界線
| 観点 | 正当なクレーム | カスタマーハラスメント |
|---|---|---|
| 要求内容 | 購入した商品に初期不良があったため、交換を求める。 | 自身の過失で商品を破損させたにもかかわらず、新品への無償交換を執拗に要求する。 |
| 手段・態様 | 事実を冷静に伝え、企業のルールに則った対応を求める。 | 大声で怒鳴り、机を叩き、他の顧客がいる前で従業員を罵倒する。 |
| 時間的拘束 | 問題解決に必要な範囲での話し合い。 | 解決策を提示しても納得せず、何時間も電話を切らせない、または店舗に居座り続ける。 |
| 要求の対象 | 企業や店舗としての公式な謝罪や対応を求める。 | 従業員個人に土下座を強要したり、個人の連絡先を要求したりする。 |
| 金銭的要求 | 商品の不具合によって生じた直接的な損害(例:クリーニング代)の補償を求める。 | 「精神的苦痛を受けた」として、社会通念を逸脱した高額な慰謝料を要求する。 |
この判断基準を社内で共有し、従業員が「これは対応すべきクレーム」「これは組織として対応を打ち切るべきカスハラ」と判断できる基準を持つことが、従業員を守るための第一歩となります。
カスハラ対策を怠った場合のリスクと罰則
法改正への対応は、企業の存続に関わるリスク管理の一環です。「罰則がないなら、後回しにしてもいいか」という考えは非常に危険です。ここでは、対策を怠った場合に企業が直面する具体的なリスクを解説します。
直接的な罰則規定はない
まず結論として、改正労働施策総合推進法には、カスハラ対策を講じなかったこと自体に「懲役〇年、罰金〇万円」といった直接的な刑事罰の規定は設けられていません 。しかし、これは「罰則がないから何もしなくてよい」という意味では決してありません。
行政による助言・指導・勧告・企業名公表の対象に
法律違反が認められた場合、企業は行政指導の対象となります。
- 助言・指導:まず、管轄の労働局から、対策を講じるよう助言や指導が行われます。
- 勧告:指導に従わない場合、より強制力のある「勧告」が出されます。
- 企業名公表:勧告にも従わない悪質なケースでは、最終手段として厚生労働大臣がその企業名を公表することができます 。
「企業名の公表」は、社会的な信用を重んじる日本企業にとって極めて大きなダメージとなります。長時間労働など他の労働法違反の事案でも、企業名が公表された事例は存在し、取引の停止や優秀な人材の採用難、ブランドイメージの失墜など、事業の根幹を揺るがす事態に発展しかねません。この行政措置こそが、実質的な「罰則」として機能するのです。
安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性も
企業が負うリスクの中で、最も直接的かつ金銭的な打撃となりうるのが、民事上の損害賠償責任です。
企業には、労働契約法第5条に基づき、従業員が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう配慮する「安全配慮義務」が課せられています 。カスハラ対策が法律で義務化された以上、企業が適切な対策を怠った結果、従業員が精神疾患を発症したり、退職に追い込まれたりした場合、この安全配慮義務に違反したと判断される可能性が非常に高くなります。
そうなれば、被害を受けた従業員やその家族から、治療費、休業損害、慰謝料などについて高額な損害賠償を求める訴訟を起こされるリスクがあります 。過去のハラスメントに関する裁判例を見ても、企業の安全配慮義務違反を認める判決は数多く出ており 、カスハラも例外ではありません。
法改正への対応を怠ることは、刑事罰の有無にかかわらず、企業の社会的信用と財務基盤を著しく毀損する重大な経営リスクであると認識する必要があります。
2025年カスハラ対策に関するよくある質問(Q&A)
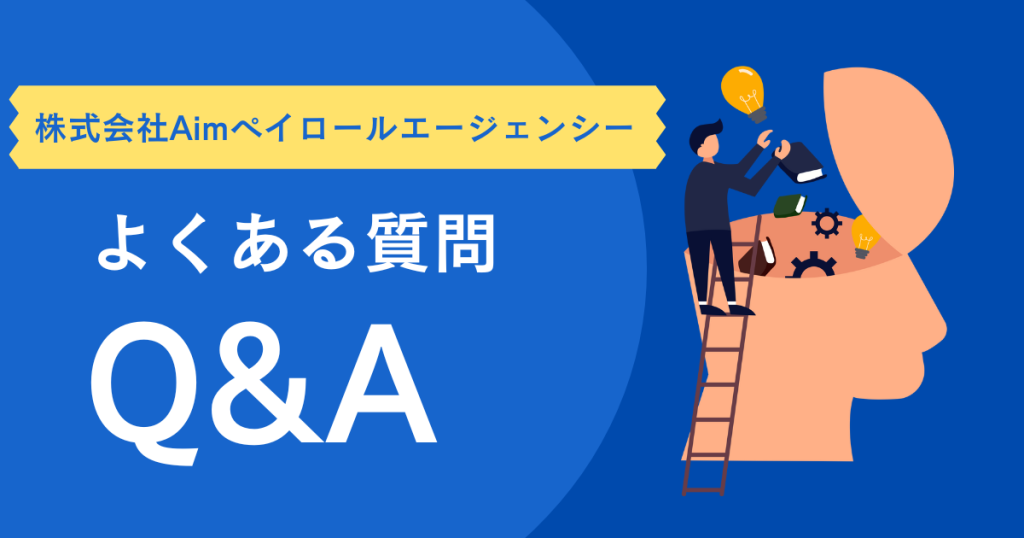
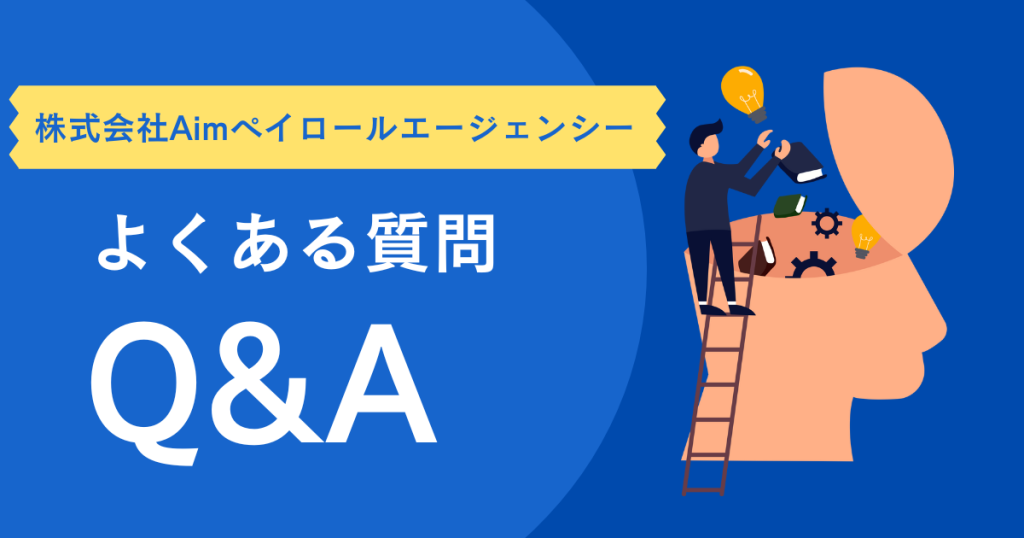
最後に、特に中小企業の担当者の方からよく寄せられる実践的な質問について、Q&A形式でお答えします。
Q. マニュアルは厚生労働省のものをそのまま使えますか?
A. 厚生労働省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」は、対策を検討する上で非常に優れた参考資料であり、必ず目を通すべきものです 。しかし、これをそのまま自社のマニュアルとして使用することは推奨されません。
マニュアルはあくまで一般的なモデルであり、最も効果的な対策は、自社の業種(例:小売業、BtoB、コールセンター)、顧客層、企業文化、組織体制といった個別の事情に合わせてカスタマイズされたものです 。例えば、対面接客が多い店舗と、法人向けの営業部門とでは、想定されるカスハラの具体例や初期対応の方法が異なります。厚労省のマニュアルを土台としながら、自社で過去に発生した事例やヒヤリハットを分析し、自社の実態に即した「生きたマニュアル」を作成することが重要です。
Q. 相談窓口は社内に置くべき?外部委託でも良い?
A. 相談窓口の設置方法は、社内に設置する方法と、弁護士事務所や専門のサービス会社に外部委託する方法の2つがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
- 社内窓口
- メリット:コストを抑えられる、社内の事情に詳しいため迅速な対応が期待できる 。
- デメリット:「相談したことが人事評価に影響するのではないか」「情報が漏れるのではないか」といった従業員の不安から、相談をためらってしまう可能性がある。また、担当者の専門性や中立性の確保が課題となる 。
- 外部窓口
- メリット:第三者機関であるため、従業員が安心して相談しやすい。プライバシーが保護され、公平な対応が期待できる。法律やメンタルヘルスの専門家による質の高い対応が可能 。
- デメリット:委託費用が発生する。社内の細かい事情や人間関係を把握していないため、初期のヒアリングに時間がかかる場合がある 。
企業の規模やリソースに応じて選択することになりますが、特に専門の担当者を配置することが難しい中小企業にとっては、従業員の安心感を確保し、専門的な対応を担保できる外部委託は非常に有効な選択肢と言えるでしょう。
Q. 従業員が少ない中小企業でも、すべて対応が必要ですか?
A. はい、必要です。前述の通り、カスハラ対策の義務は事業規模にかかわらず、すべての企業に適用されます。
ただし、求められる対策の「規模」や「具体的方法」は、企業の状況に応じて柔軟に考えることができます。例えば、従業員数名の企業で、人事部や法務部といった専門部署を設置することは現実的ではありません。
重要なのは以下の3つです。
- 方針の明確化:経営者が朝礼などで直接、カスハラを許さない方針を伝える。
- 相談担当者の指名:特定の役員や信頼できる従業員を相談担当者として指名し、その旨を全員に周知する。
- 対応プロセスの簡易化:問題が発生した際は、「すぐに経営者に報告する」というシンプルなルールを徹底する。
義務の核となる部分を確実に実行することが重要です。重要なのは、形式ではなく、従業員が「何かあったら会社が守ってくれる」と実感できる実質的な仕組みを構築することです。
まとめ


本記事では、2025年の法改正によって義務化されるカスタマーハラスメント対策について、その概要から企業が取るべき具体的な行動、そして対策を怠った場合のリスクまでを網羅的に解説しました。
まずは本記事で紹介したチェックリストや文例を活用し、自社の現状把握から始めてみてはいかがでしょうか。